この記事のポイント!
・梶原氏は、源平の時代から続く武家の名門
・毛利氏や本願寺、雑賀衆などと協力し、三木城に兵糧物資の支援をした
・梶原氏のいた高砂城は、その所在がいまも謎
梶原氏
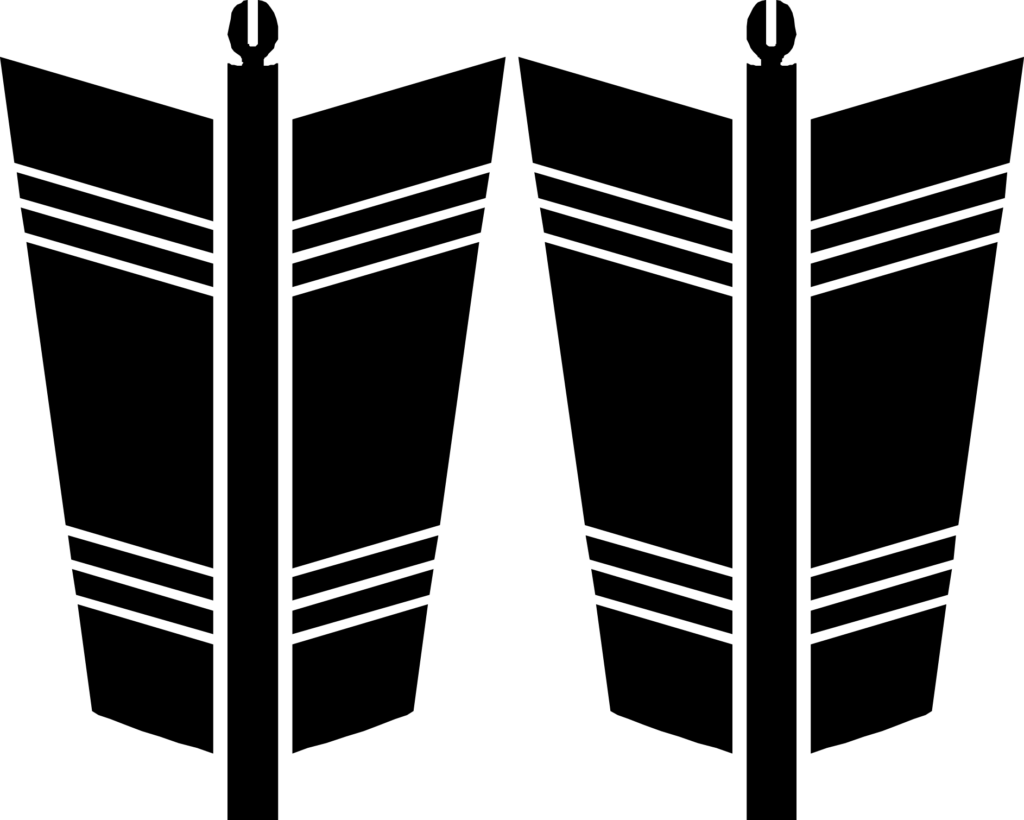
梶原氏は桓武平氏の流れを汲むと言われ、 相模の国(神奈川県)の鎌倉に近いところに所領を持っていました。
源頼朝とも深い関係であったようで、源平合戦では水軍の将として瀬戸内海の水軍を取り纏め、屋島の合戦で大活躍しました。
しかし、頼朝死後は不遇の時代となる。同じ御家人の結城氏や三浦氏と権力争いが生じ、鎌倉を追放される。一族は、水軍のつてをたどって紀州・沼島・阿波・播磨などに散らばりました。
播磨高砂の梶原氏の始まりです。
毛利氏・本願寺・紀州雑賀衆らと三木城を支援す
籠城を余儀なくされた三木城の別所氏を支援するため、西国の雄・毛利氏、摂津石山(大坂)本願寺、紀州の鉄砲集団・雑賀衆などが明石・魚住や高砂から兵糧や物資の補給を行っていました。高砂城からも大量の物資が加古川を登り、室山付近で陸揚げされて三木城へ運ばれました。
この状況を見た秀吉軍は、輸送路を断つために高砂城を攻めます。
「かちんの直垂に、萌黄威しの鎧を着て、頭なりの甲(かぶと)をまとって、鹿毛の馬に金覆輪の鞍を置き、早咲きの紅梅を箙(えびら:矢を入れる筒)に差して」
(播州太平記)
勇猛果敢に戦ったと描写されています。しかし、衆寡敵せず、劣勢となった景秀は一族を三木城へ入れ、自身は鶴林寺へ身を寄せた(とも伝わります)。
謎の高砂城
梶原氏が秀吉軍と戦った「高砂城」はどこにあったのか?まだ、謎のままです。
現在、高砂神社のある場所には、姫路城に池田輝政が入った時に支城として築城した「高砂城」があったとされています。(その後破城され、高砂神社が元に戻ってくる)
また、少し北の小松原というところに、三社神社があり、そこがかつての「小松原城」跡となっています。ここが梶原氏がいた古城高砂城だとの説もありますが、石碑には赤松一族の小松原家が築城としか記載がありません。
ということで、いまだに梶原氏の高砂城はどこなのか、謎のままです。
御城印・武将印


関連スポット
| 史跡名 | 場所 | 概要 |
|---|---|---|
| 高砂城 | 兵庫県高砂市 | 池田氏の姫路入封時に築城した城。梶原氏の高砂城は正確な位置などは分かっていない。 |
| 小松原城 | 兵庫県高砂市 | 赤松氏系の小松原氏が築城したと伝わる城。 |
| 十輪寺 | 兵庫県高砂市 | 梶原氏の墓所、および出身の三浦半島から逃れてきた三浦氏の墓所もある。 |

2件のコメント